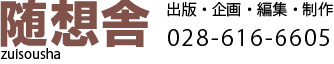ボクが地方出版をはじめた理由
卯 木 伸 男(随想舎取締役社長)
加齢なる変身
五十半ばを過ぎて老眼鏡をかけるようになった。それまで掛けていた眼鏡が見えにくくなったので度数をあげたら、今度は手元が見えづらくなってしまったのだ。新聞おろか、読書をするのにも事欠く始末。これでは校正などできるはずがない。ましてやパソコンを見つめていると、肩や首筋が張ってしまい作業効率の低下は著しい。そこで、まだ若い(?)とかっこをつけても仕方がないと覚悟を決め、老眼鏡を掛けるようになったしだいである。
しかし、思えば齢も杖家はとうに過ぎたのだから老眼鏡はいたって自然な成り行き。それにこの稼業に入って来年で三十五年、人よりも我が眼を酷使してきたのだから、むしろ老眼鏡は遅いくらいだったのかもしれない。先だっては重い荷物を持ったわけでもないのに、突然、ぎっくり腰になってしまった。返本の山を前にしての出来事なら笑い話にもなるが、朝、ベッドから起き出したら発症していたというから笑えない。この摩訶不思議な状況に、「加齢なる変身」を遂げたと我ながら感心している。
こんなボクであるが、年上の友人と二人で随想舎を設立したのは、一九八五年一月、二十七歳のとき。友人とは昨年惜しくも七十一歳で亡くなった長野県生まれのO氏、彼とて三十七歳の若さだった。知り合ったのは、いまは無き「仮面館」というライブハウスで、年齢の差はあるものの妙に馬が合い長い歳月を共に歩んできたのだ。まさに光陰矢の如し。歳月が経つのは早いものだ。

信州で出会った地方出版
ボクは大学の四年間を長野県上田市で過ごした。この四年間がボクの今を決定づけたと言ってよい。その理由は長野県で初めて地方出版たるものを見聞きし、その存在感に驚愕と憧憬を抱いたからである。それまでボクが暮らした栃木県にも地方出版社は存在したが、その規模、多種多様なテーマにはどう足掻いてもかなわなかった。
さらに、県都長野市は言うに及ばす、松本、上田、飯田市をはじめ軽井沢町など各地域に出版社があり、野武士のような貫禄と光を放っていた。また、どこの書店にも地方出版の棚が設けられているのにも驚いた。それは地方から初めて東京に出てきたとき感じるカルチャーショックそのものだった。
それまでのボクはどちらかと言えば、文筆家志望だった。誤解がないように言っておくが、決して実力があったわけでも才能があったわけでもない。ただ、幼いころから作文や本が好きで、大学に入ってからは同人誌やミニコミ誌などを発行し、一人悦に入っていただけのことである。しかし文筆家で食えるほど世の中甘くはない。だからと言って新聞社や出版社への就職を真剣に考え行動したかというとそうではないまったくと言っていいほど、何もしなかった。強いて就活と言えば、大学四年生のときに教授の紹介でタウン誌を創刊するという創業百年近い活版会社に面接へ行ったことを憶えている。地方・小出版流通センターの図書目録を見ると、その会社は今も健在。小海線沿いの町で地道な出版活動を続けていた。
出版社という印刷会社で学んだこと
ボクは就職活動もしないまま大学を卒業し、職安の紹介で宇都宮にある「出版社」と名がついた印刷会社に転がり込んだ。なぜその会社に就職したかと言えば、答えは簡単。安直なようだが、前述した通り単純に出版社希望だったからだ。それにボクは学生結婚で、生まれたばかりの娘がいたから生活費を稼ぎ出すのは至上命題だったののである。工場の裏側に建てられた二軒続きの社宅住まい、額面八万五千円が初任給だった。
就職はしたものの右も左も分からないことばかり。B4、A5の判型おろか、印刷の仕組みなど分かるはずがない。版下と製版を中心に、それこそ見よう見まねで仕事を覚え、毎月数十時間の残業を黙々とこなした。
しかし、退職するまでの六年間に体得した印刷の知識と技術は、いま出版を生業とする上でそれこそ強力な武器になっている。印刷現場を知らない頭でっかちな編集者にならないで良かったと常々思う。

編集者の本領
一冊の本はさまざまな人の手によってつくられている。もちろん書き手たる著者なしでは始まらないが、別の視点から見れば著者ひとりだけでは、成り立たない。本は書き手とつくり手との共同作業なのだ。ここで重要なのが編集という仕事。大先生の作品であってもそれは同じである。編集作業を経て、初めて世に送り出されると言ってよい。原稿だけみても著者から持ち込まれる場合もあれば、版元(出版社)が企画を立てて著者になりうる人物を探して依頼することもある。その先頭に立つのが編集者なのだ。
編集者というと一見華やいだ職業にも思えるが、実は地味で根気がなくてはつとまらない重労働。残業おろか土日出勤もあたりまえ。一握りの大手版元を除けば、低賃金が大手を振ってまかり通る業界である。
先日、書店の紹介で出版社希望の女子大生が採用予定の有無を問い合わせてきた。今春、卒業予定なのだが、まったく内定がもらえず落ち込んでいるらしい。採用の予定は無いことを前提に、話だけでもと来てもらった。聞くところによると、首都圏の出版社をかたっぱしからエントリーしたが、面接までこぎつけないとのこと。大手版元はいざしらず、零細版元は即戦力になる経験者しか採用できないのではと、業界の現状を説明してお帰りいただいた。
また、出版業界には死語ともいえる(?)「志」という言葉が、まことしやかにささやかれている。ボクもその「志」とやらに毒されている一人だが、食えなくてはしょうがない。本も売れなければ、版元としてたち行かない。本は読まれて(買っていただき)はじめて意味を持つ。
しかし、そうは言っても志だけではなかなか当たらないのが業界の常。二○一八年の新刊点数は約七万三千点にものぼる。一年三百六十五日に換算すれば、毎日二百五冊もの本が誕生していることになるから、いやはやすごい数字だ。返品率も四十%を超える。新刊の書店滞在時間が短いのも頷ける。
小社では、人文系のいわゆる「堅い本」が多い。その内容にもよるが、売れて確実なところ千冊を超えるくらいか。「売れれば官軍。売れなければ賊軍」とのそしりも受けるが、地方で版元をやる以上、心がけることは古びない本をつくることにつきる。評論家の大宅壮一が著書『実業と虚業』の中で、出版社には「漁業説」と「農業説」があると書いている。漁業説は「魚の大群をいちはやく発見し網を打ち、ベストセラーをねらうもの」、農業説は「土地を耕して、わずかだが確実な収益をあげていくもの」とあり興味深い。小社はどちらかと言えば後者。できうれば、著者と共同して地方をモチーフにしたものであっても底本になるような企画を出し続けていきたいと思う。
本と言えるのは、モチーフを愛した編集者が介在したもの。いくら体裁を整えていても、編集されていない本は単なる印刷物に過ぎない。好奇心を忘れず、著者の意図を理解し、読者にいかに的確に伝えるかが編集者の本領である。

事務所を開いて三十五年
さて本題であるが、ボクが随想舎を始めた理由はただひとつ。無謀であるが印刷会社の将来性と就職試験の煩わしさを思えば、自分で出版社をつくってしまった方が簡単だと考えたからだ。家賃一万五千円の畳屋倉庫の二階を根城に、三十万円を二人で出し合い購入したワープロ一台と、定規、カッター、ピンセットが今日の始まりだった。まったく資金も、事業計画もないままのスタートだったのだ。そのせいか、開店祝いならぬ宴会の席では、「『随想舎』が『瞑想者』にならないように」とか、「栃木県で出版は無理。もって一年」と友人たちが真顔で心配してくれたことを昨日のことのように思い出す。
社名は編集プロダクションを意識して、「編集工房随想舎」(随想舎は会社登記から)となづけた。それは当初から闇雲に出版を始めるのではなく、かつての伝手で印刷会社から制作などの仕事を貰いながら体力がついたら出版を始めようと考えていたからだ。そのため社内に電算システムを構築し、編集から組版、出力まで一貫して行える態勢を整えた。これは宇都宮でも最も早いものだったと思う。
二、三年が経ち自費出版の受注も増え、何とか糊口が凌げるようになったころ出版した第一作が、全国労農大衆党と大日本生産党の武力衝突を描いた『曙光-実録「阿久津村騒擾事件」』だった。たぶん全国取次店の地方・小出版流通センターともこのころ取引を開始したのだと記憶している。
あれから三十五年。数えれば出版点数は五百点を超えた。田中正造や足尾銅山関係のラインナップは小舎ならでは。定期刊行物、記念誌をはじめ委託・自費出版は枚挙に暇がない。事務所も倉庫の二階からビルに移った。社員もボクを含めて七人の所帯に増えた。老眼鏡を掛け、腰を労りながら、図書目録を財産に地方出版の先輩諸氏を見習って喜寿の年まで頑張ってみようか。